警備業界では、人材不足・高齢化・長時間労働・労務管理の厳格化といった複数の課題が同時進行しています。2024年からの時間外労働の上限規制、教育や配置に関する証跡管理の義務化など、従来の紙・電話・Excel中心の運用だけでは対応が困難な状況が生まれつつあります。
現場の努力や精神論だけでは守り切れない領域が増えた今、「仕組みで現場を守る」 という経営発想が欠かせなくなっています。その中心にあるのがDX(業務デジタル化)です。小さく始めても効果が出やすい領域から取り組むことで、人員不足に左右されない会社運営、事故・トラブルの未然防止、管制業務の安定化が実現できます。
警備会社が抱える3つの構造的課題
① 深刻化する人手不足と採用・教育コストの増大
警備業の有効求人倍率は依然として高く、採用コストは年々上昇。採用できても定着しにくく、教育や配置の手間が発生し、「採っても人が足りない」悪循環が起きやすい構造があります。
- 平均年齢の高齢化(若手確保が進まない)
- 採用単価の上昇(月10〜50万円のケースも)
- 定着率が低く教育投資が回収できない
この状況では “既存戦力をどれだけムダなく・辞めさせず・リスクなく運用できるか” が最大テーマとなり、結果として 「勤怠・配置・教育のDX」が最も費用対効果の高い投資になります。
② 法令遵守に伴う管理コストの増大と“紙文化の限界”
2024年以降、労働時間管理・教育記録・有資格者配置・健康管理など、証跡管理のハードルは確実に上がりました。警備は現場が分散し社員常駐型ではないため、紙・Excel運用だと次の課題が発生します。
| 現場で起きていること | 原因 |
|---|---|
| 配置ミス・教育記録漏れ | 情報が分散・属人化 |
| 報告書回収遅れ | 紙/FAXベース |
| 労務違反の見落とし | 勤怠のリアルタイム把握不可 |
| 監査・是正で混乱 | 証跡の所在がバラバラ |
つまりアナログ運用は 「ヒューマンエラーを前提とした仕組み」であり、法律が求める精度・スピードと相性が悪いのが構造的な問題です。警備DXは「業務効率化」だけでなく 「法令違反・事故・トラブルという会社存続リスクから身を守る防御策」として機能します。
③ 管制と現場の情報断絶による慢性的な業務ひっ迫
現場変更・欠員対応・異常連絡など、警備の情報は 「緊急性が高く、即時に判断が必要」 なものばかりです。しかし電話中心の運用は次のような問題を引き起こします。
- 夜ほど電話が鳴り止まない
- 報告書が遅れ、本部の判断が常に後追い
- 誰が何を把握しているか“人”に依存
- 緊急時に過去記録が追えず初動が遅れる
この状態を続ける限り、管制の負担は増え続け、現場の安全性・会社の判断精度・顧客満足度のすべてが下がります。
必要なのは 「現場 → 管制 → 経営」まで情報をリアルタイムで一本化する仕組みです。

中小警備会社でも始めやすい「3ステップDX」
警備業務は負荷の大きい領域が明確なため、次の順番で進めると最小コストで最大効果が出ます。
| ステップ | DX領域 | 目的 |
|---|---|---|
| STEP1 | 勤怠・シフトDX | 労務リスクと管制負担を最小化 |
| STEP2 | 報告DX | 現場の記録と情報共有をリアルタイム化 |
| STEP3 | 省人化DX | 夜間業務や定型タスクの自動化 |
以下では、それぞれの領域で“実際に現場で成果が出やすい代表ツール”として1部をご紹介します。
STEP1:勤怠・シフトDX(労務と管制の負担を劇的に減らす第一領域)
警備業の勤怠管理は業界特有の複雑さがあります。
「現場ごとに条件が違う」「休憩と拘束を分けて管理」「複数現場を掛け持ち」「隊員の開始・終了が深夜や早朝に散らばる」という特徴から、紙とExcelでは管理側の限界がすぐに訪れます。勤怠・シフトDXは、この状況を “リアルタイム・自動・見える化” によって根本から改善する領域です。
<できることの代表例>
- 上下番報告のデジタル化(スマホ打刻・GPS連動など)
- 労働時間の自動集計・長時間労働のアラート
- 有資格者配置の自動チェック(警備業法の違反防止)
- シフト自動作成・欠員時の即時周知
<導入効果>
- 管制電話・手入力・転記作業が大幅に削減
- 労務証跡が残り、監査・是正対応が迅速に
- 配置ミス・入力ミスなどのヒューマンエラーが減少
- 「勤怠の透明性」が担保され、隊員トラブルも減少
<代表的なツール例(公式リンク)>
- KING OF TIME(勤怠基盤として導入実績多数) https://www.kingoftime.jp/
- ジョブカン勤怠管理(現場打刻に強い) https://jobcan.ne.jp/
- SiftMax(警備業界でも指示されている) https://shiftmax.co.jp/
STEP2:報告DX(紙・FAX・Excelからの脱却で“現場の今”が見える業務へ)
報告書業務は紙文化が最も残りやすい領域です。
- 「報告書回収が遅れる」
- 「手書きの品質にバラつき」
- 「証跡が残らず口頭ベース」
- 「現場と本部で認識がズレる」
こうしたトラブルが日常的に起きています。報告DXは、この領域を “誰が見ても・いつ見ても・同じ情報になっている状態” に変えます。
<できることの代表例>
- 巡回・点検記録のリアルタイム共有
- 異常発生の即時連絡と本部への自動通知
- 写真・動画を使った客観的な証跡保存
- 報告書のフォーマット統一(属人化防止)
<導入効果>
- 初動判断が早くなる(事故対応力の向上)
- 報告品質が均一化され、クレーム火種を削減
- 記録の抜け漏れがゼロに近づく
- 本部が現場の状況をリアルタイムで“見てから判断”できる
<代表的なツール例(公式リンク)>※STEP1の”勤怠・シフトDX”もカバー!
- プロキャス警備(警備特化の勤怠・配置DX) https://pro-cas.jp/keibi/
- KOMAINU(こまいぬ)(現場管理〜管制向け) https://komainu.cloud/
- KeiBiz(警備に必要な業務が全て集約) https://keibiz.olude.jp/
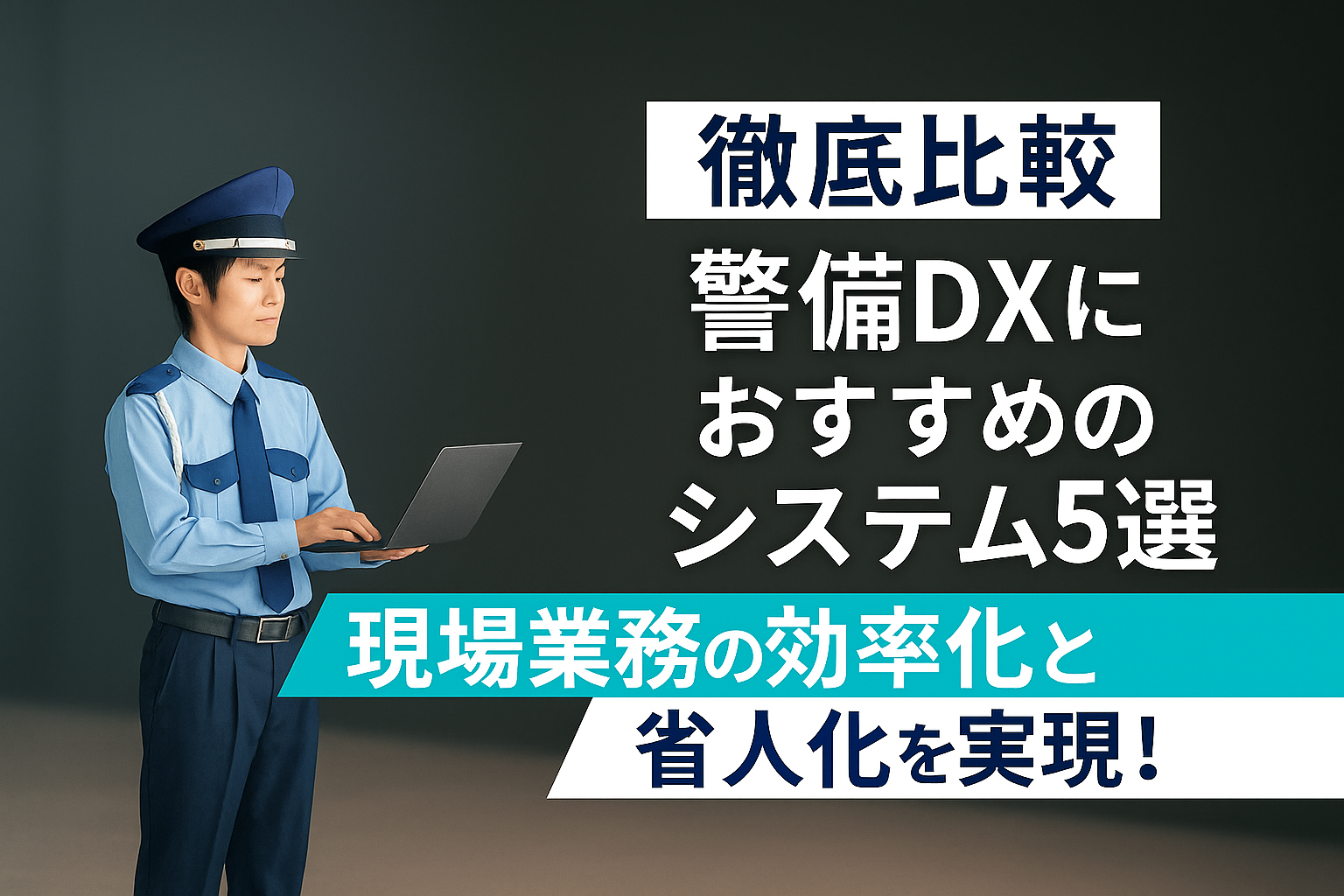
STEP3:省人化DX(AI警備ロボットで夜間巡回の自動化と安全性を両立)
夜間巡回・定点監視は 「危険・定型・負担が大きい」 という警備業務の中でも最もDX効果が大きい領域です。省人化DXの中心となるのが AI警備ロボット です。目的は 人を減らすことではなく、人が無理をしなくていい現場を作ること。省人化DXは「安全・省力・継続性」を生みます。
<できることの代表例>
- 自律巡回・異常検知・遠隔声かけ・威嚇
- カメラ・サーマル等による監視と通知
- 記録を自動保存し、事故の検証にも活用可能
- 省人化による固定費削減と人員再配置
<導入効果>
- 夜間巡回の人的負担と危険リスクを削減
- 「巡回漏れ」「見落とし」のヒューマンエラーを防止
- 1名配置現場のリスクを大幅緩和
- 人材不足時でも現場が回る体制づくりが可能
<代表的なツール例(公式リンク)>
- ugo(ユーゴー) https://ugo.plus/
- cocobo(ココボ) https://www.secom.co.jp/business/cocobo/
- SQ-2(屋外巡回モデル) https://www.seqsense.com/
補助金で導入コストを抑える(IT導入補助金の活用)
DX導入において最大の障壁は「コスト」です。そこで有効なのが IT導入補助金 です。
<ポイント>
- 最大350万円(年度により変動)
- 対象ツールであれば導入負担を大幅に軽減
- 勤怠・報告領域は対象になりやすい傾向
“まず負担なく導入 → 効果確認 → 全社展開” という現実的なDX戦略を取りやすくなります。
DXを成功させる7つの原則

- 領域を1つに絞って始める(全部一気にやらない)
- 現場テスト導入(スモールスタート)
- 現場が使えるUIを優先(難しいDXは定着しない)
- 紙とデジタルを並走させない(移行期を短く)
- 属人管理を前提としたルールを廃止
- 投資対効果は“労務時間・トラブル減”で評価
- サポートが強い提供会社を選ぶ
まとめ|DXは“守りと攻め”の両面で会社を強くする
警備DXは贅沢でも流行でもありません。「人手不足の時代に、会社と現場を守るための必然的な経営手段」です。
- 勤怠・配置が整う(守り)
- 報告と判断が早くなる(守り+攻め)
- 省人化で強い運用に変わる(攻め)
この順番で整えることで、管制も現場も疲弊しない会社運営が実現します。まずは領域を1つに絞り、DXを小さく始めてみてください。最初の1歩が、現場と経営を確実に変えていきます。
警備NEXT(警備ネクスト)では、現場で役立つ知識や警備員の声をこれからも発信していきます。日々の勤務に少しでも役立ててもらえたら幸いです。
