変革期を迎える警備業界
近年、警備業界は大きな転換点を迎えています。少子高齢化に伴う人材不足や、テクノロジーの進展、制度改革、さらには国際的な人材の活用など、業界を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。
2025年以降、警備業を取り巻く社会課題や行政の対応、民間企業の取り組みはますます加速していくと見られており、業界全体の変化は「待ったなし」の状況です。
この記事では、2025年に注目すべき「警備業界の動向」を5つに厳選して紹介。今後の採用や現場運営、サービス品質の向上において、企業が押さえておくべきテーマを具体的に解説します。
1. 慢性的な人手不足と高齢化の加速

警備業界の「人手不足」はいよいよ構造的な課題に
警備業は他業種と比較して高齢化が顕著で、平均年齢は60歳を超えるとされる現場も少なくありません。若年層の確保が難しい中、今後は「採用できない」ことを前提とした運営体制の構築が必要になります。
例えば、下記のような傾向が続いています:
- 深夜・休日勤務の応募が減少
- 体力面から60代以上の従事が難しくなる
- 有資格者(交通誘導2級など)の不足
この背景には、体力的なハードルに加え、業務内容の単調さや社会的評価の低さ、長時間拘束などの要因も関係しています。
また、2025年問題(団塊の世代の後期高齢者入り)により、さらに人材供給は減少し、代替手段が求められる時代に突入しています。
今後は「採用」だけでなく、「定着」「再雇用」「副業人材の活用」など、多面的な人材戦略が必要となるでしょう。
さらに、国の政策として「生涯現役社会」の実現に向けた取り組みも進んでいます。シニア世代が安心して働き続けられるよう、業務内容の見直しや適切な休憩・配慮も重要です。
警備業務を細分化し、体力に依存しないポジション(受付・監視業務など)へのマッチングも重要なテーマになりつつあります。高齢者や女性が安心して働ける環境づくりが、今後の安定運営に直結するでしょう。
2. DX(デジタル化)による業務効率化の加速
アプリ・クラウド・AIによる警備業務の革新
人手不足を補う手段として、近年はDX(デジタル・トランスフォーメーション)の導入が急速に進んでいます。特に以下のようなツールが導入されています:
- 勤怠管理アプリによる打刻・シフト管理の自動化
- チャットやLINEを活用した現場連絡の円滑化
- クラウドでの報告・写真添付・日報作成の効率化
- AIによる警備配置や警備対象リスクの可視化・予測
- 警備ロボット・監視ドローンによる巡回の代替
これらは単に業務を効率化するだけでなく、現場における情報の可視化、管理者の負担軽減、従業員の満足度向上にもつながっています。
特に注目されるのは、若年層へのアプローチです。スマホ一つで勤怠・連絡・申請が完了する仕組みは「働きやすさ」と直結し、企業ブランディングにもつながります。
さらに、セキュリティIoTや生体認証システムの導入も進んでおり、今後の警備業は「人とデジタルの共存」がテーマとなるでしょう。DXは単なる効率化手段にとどまらず、業務の質と信頼性を高めるツールとして今後も注目されます。
このようなツール導入にはコストもかかりますが、業務時間の短縮、報告ミスの削減、社員満足度の向上という“投資対効果”が得られる点で、導入する企業が増えています。初期投資の回収までの期間を明確に設定することで、社内説得もスムーズになります。
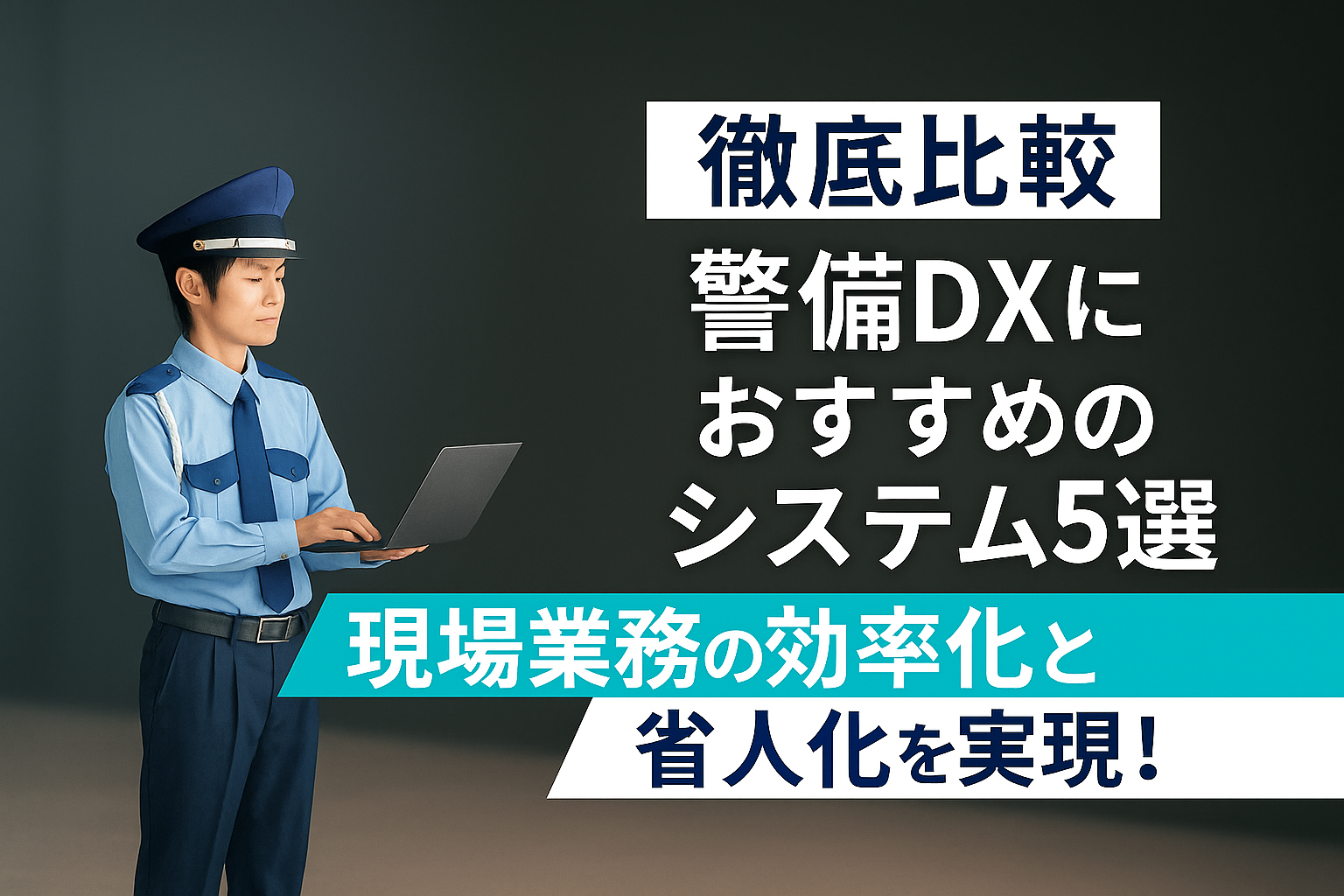
3. 警備業界における外国人活用の可能性と現状
3.1 現在の就労可能な在留資格
現時点で警備業に外国人を直接雇用できる在留資格は限定的ですが、以下のようなケースでの実務参加が一部で確認されています。
- 永住者・定住者・日本人配偶者等:在留資格に制限がないため、警備業務も従事可能。
- 留学生・技能実習生:原則として警備業務は不可。ただし、派遣会社や研修機関を介した清掃・軽作業との兼務が可能なケースも。
3.2 現場でのニーズと懸念
実際の現場では、「深夜・休日に働ける人材が確保しづらい」「若年層の応募が集まらない」といった課題があり、外国人材の活用に関心を示す企業も増えています。
一方で、「日本語能力の不安」「警備業法による制限」「顧客からの理解が得られるか」といった懸念も根強く、現時点では“慎重な検討段階”という企業が多数派です。

4. 今後の制度拡大と警備業への影響
警備業界が外国人材を受け入れるには、以下のような制度的・業界的な変化が必要とされています。
| 必要な変化 | 説明 |
|---|---|
| 警備業法の見直し | 外国人が警備業務に従事する際の規定整備(例:語学要件、身元保証制度など) |
| 資格試験の多言語化 | 警備員指導教育責任者・検定試験などの英語/多言語対応 |
| 雇用管理体制の強化 | 文化・宗教・労働慣習への理解を踏まえた就業環境の整備 |
| 顧客側の理解促進 | 警備先企業・自治体との情報共有やトラブル防止策の明示 |
政府や業界団体による検討会も進んでおり、2026年以降には実証事業などを経て一部警備業務での外国人活用が可能になるとの見方もあります。
5. 警備企業が今できる備えとは?
現時点で外国人警備員の本格雇用は難しいものの、企業としては以下のような準備を進めておくことが重要です。
- 外国人材に対応できる研修制度の整備
- 就業規則や管理マニュアルの多言語対応
- 清掃・受付・施設管理など関連業務での外国人活用からのステップ導入
- 「外国人材活用に関する自治体支援制度」の活用(例:受け入れコンサル、助成金)
特に、永住者や定住者など既に就労可能な在留資格者に対しては、派遣会社や紹介サービスを通じたトライアル採用も現実的な第一歩となるでしょう。
警備業界に求められる“次の担い手”の視点
外国人材の活用は、警備業界の構造的な人材不足に対する一つの有効策となり得ます。すぐに全面導入が可能な状況ではありませんが、制度改革と現場の受け入れ体制が整えば、新たな戦力として期待が高まります。
今後の法整備や政策動向を見据えながら、まずは“備え”として社内環境の見直しと意識改革を進めておくことが、競争力ある企業づくりの一歩となるはずです。
警備の”今”と”これから”を考えるメディア「警備NEXT」では業界ニュースや現役警備員から聞いた調査レポートを掲載しています。ぜひ参考にしてみはいかがでしょうか。
