2024~2025年にかけ、警備業界にとって注目すべき法改正がいくつか施行されました。警備員として働く方、または警備業を運営する企業にとって、「今後の制度にどう備えるべきか」は大きな関心ごとではないでしょうか。今回の法改正は、現場の働き方、教育制度、管理体制に至るまで、あらゆる面で変化をもたらしています。
本記事では、警備業法改正の主なポイントを現場目線でわかりやすく解説し、警備業界の最新動向や対応策も併せて紹介します。制度理解を深め、変化の中でも安心して働き続けるために、ぜひ最後までお読みください。
警備業法とは?その役割と基本情報

警備業法の概要
警備業法は、警備業務に従事する企業や警備員が守るべきルールを定めた法律です。1972年に制定され、社会の安全と秩序を維持するための重要な枠組みとして位置づけられています。年々進化する治安情勢や社会のニーズに対応するため、これまでにも幾度となく見直されてきました。
警備業には主に以下の4つの業務区分があります。
- 施設警備業務:ビル、商業施設、工場などの施設を対象とした警備
- 交通誘導警備業務:道路工事や建設現場などで車両・歩行者の誘導を行う
- 雑踏警備業務:イベント会場やお祭りなどでの人混みの整理・安全確保
- 身辺警備業務:いわゆるボディーガード。人の生命・身体の安全確保を目的とする
それぞれに求められるスキルや判断力が異なるため、法律でも適切な教育や管理体制が義務付けられています。
なぜ警備業法の改正が必要?
社会の変化に応じて、警備の役割も進化しています。たとえば、大規模災害時の避難誘導や、学校・病院での防犯強化など、警備業務は従来の「見張る・防ぐ」から「守る・助ける」へと広がりを見せています。
また、2020年代に入り、日本全体で高齢化が進行する中、警備業界でも60代以上の従事者が急増。警察庁「令和5年における警備業の概況」によると、2023年末時点で警備員のうち65〜69歳は13.6%、70歳以上は20.1%に達しており、合わせて約33.7%が65歳以上となっています(出典:警察庁統計資料)。
さらに、同資料によると女性警備員は4万975人で、全体の約7.0%を占めています。近年は女性の採用を積極的に進める企業も増えていますが、依然として少数派であり、多様性の確保が今後の課題となっています。
若年層の担い手が不足する一方で、技術革新やAIの活用が求められるようになりました。こうした時代背景を踏まえた制度改正が、2024~2025年に実施されたのです。
2024~2025年にかけて改正・施行された主なポイント
警備業法改正では、以下の5つの点が大きく変わりました。
- 教育制度の強化:警備員に対する継続的な教育の導入や、eラーニングなどICTを活用した柔軟な研修体制の整備が行われました。
- 自主点検制度の義務化:警備業者自身による業務状況の確認・記録が義務づけられ、法令遵守と運営の透明性が強化されました。
- 外国人労働者の受け入れ基準明確化:特定技能制度を活用した外国人警備員の受け入れに関する基準と研修体制が整備されました。
- AI・ICTの導入推進と制度整備:AIカメラや警備ロボットなど先端技術の活用が認められ、法的な整備が行われました。
- 働き方の多様化支援:高齢者や女性、外国人など多様な人材が働きやすい環境整備が求められるようになりました。
このように、法改正は単なるルール変更にとどまらず、業界全体の構造改革を後押しする重要な契機となっています。
法改正前後の違い【比較表】
| 項目 | 改正前(〜2024年) | 改正後(2025年〜) |
|---|---|---|
| 教育制度 | 年1回の現任教育 | 継続教育+ICT導入 |
| 管理体制 | 主に警察の立ち入り検査 | 自主点検の義務化 |
| 外国人受け入れ | 基準不明瞭 | ガイドライン整備・文化研修推奨 |
| AI/ICT技術活用 | 法的定義なし | 法制度の明確化・活用推進 |
このように、制度面の刷新だけでなく、業界のあり方そのものが「自律」と「成長」を軸に大きく変わり始めています。
※具体的な運用内容や施行日は各トピックごとに若干異なり(一部事項は段階的施行)、細部の運用指針や省令部分は各省庁・警備業団体の公式資料でご確認ください。
警備業界を取り巻く最新動向

高齢化と担い手不足の深刻化
警備業界は慢性的な人手不足に悩まされています。若手人材の確保は困難を極めており、今後の業界維持には構造的な改革が必要とされています。
女性警備員の活躍とニーズの高まり
かつては男性中心だった警備業界ですが、施設警備や巡回業務、受付警備などで女性のきめ細やかな対応力が評価され、採用の裾野が広がりつつあります。各社では女性用ユニフォームの見直しや、休憩室・更衣スペースの整備も進んでいます。
スマート警備市場の成長
従来の「人による警備」から、「人とテクノロジーの連携」による警備体制への移行が加速しています。AIカメラ、顔認証システム、警備ロボット、IoTセンサーといった技術が実用段階に入り、巡回や監視といった業務の一部が自動化されています。
これにより、人手不足の課題を補完しながら、警備の品質や対応スピードを高める取り組みが全国で進んでいます。警備業者の中には、遠隔監視センターを設けたり、モバイル端末で現場状況を即時把握できる仕組みを導入したりと、IT活用が現場レベルまで浸透しつつあります。
スマート警備は単なる機器導入ではなく、「効率化」と「安全性の向上」を両立する戦略的な選択肢として、今後ますます重要性を増すと考えられます。
今後のカギは「現場適応力」
制度や技術がどれだけ進化しても、最終的に重要なのは「現場に応じた柔軟な運用力」です。暑さ・寒さ対策、災害時対応、不審者の早期察知、外国語対応など、現場ごとに求められる役割は多岐にわたります。業界全体でナレッジ共有と事例集の整備を進めることが、次の時代の警備の質を左右するといえるでしょう。
警備業と地域防災への貢献

災害時の「頼れる存在」として
災害発生時には、施設内外の安全確認や初動対応が重要です。警備員は常に現場にいるため、避難誘導や初期対応の一端を担える存在です。特に大規模施設や公共交通機関、病院・商業施設などでは、一般の来訪者やスタッフが混乱するなか、冷静に避難経路を案内する役割を果たします。
警備員は普段から施設の構造や導線に精通しているため、災害マニュアルに従った適切な行動をとりやすく、非常時の判断力にも信頼が寄せられています。最近では、初期消火やAED(自動体外式除細動器)の使用、応急手当などについての研修も取り入れられており、防災の“初動リーダー”としての役割も強まっています。
加えて、消防や自治体、近隣施設との連携を強化することで、地域全体での災害対応力向上にも寄与しています。こうした活動は、企業の危機管理体制の一翼を担うものとして、ますます注目されています。
高齢者・災害弱者への対応力
高齢者や障害を持つ方など、災害弱者とされる人々への声かけや誘導の役割も期待されています。特に警備員は施設内外での巡回中にこうした方々と接する機会も多く、緊急時には「最も身近にいる支援者」として機能します。
日常的な接点を通じて、車椅子利用者の移動経路や視覚障害のある方のサポートポイントなどを把握しておくことが、いざという時の支援に直結します。また、特定の持病を抱える方や、認知症の傾向がある高齢者が行動に迷った際も、的確な判断とサポートが求められます。
災害時には避難行動要支援者のリストをもとに、行政や福祉関係者と連携しながら、適切な誘導や声かけを行う体制づくりが重要です。今後はこうした分野でも、警備員の役割とスキルがますます重視されるでしょう。
地域連携による信頼構築
地域社会と連携した活動は、警備員が単なる警備業務を超えて、地域住民と共に安全を守る存在であることを示しています。防災訓練や地域見守りなど、日常的な関係づくりが非常時の対応力にもつながります。警備員が地域の顔として認識されることで、住民からの声かけや情報提供といった双方向の信頼関係が生まれやすくなります。
企業としてもCSR(企業の社会的責任)の一環として地域との連携を進めることで、ブランドイメージ向上や採用広報にも好影響が期待できます。とくに地方においては、警備員が自治体主催の訓練や教育活動に参加することで、地域の防犯力や防災意識を高める重要な存在としての役割が一層強まっています。
データと可視化による業務の質向上
クラウド活用とリアルタイム対応
クラウドシステムにより、遠隔地からでも勤務状況やシフト管理ができ、トラブル時にも素早い対応が可能になります。従来は拠点ごとの紙台帳や電話連絡に頼っていた情報共有も、クラウド化により即時反映され、指示の遅延や確認ミスを大幅に減らすことができます。
特に、複数現場を抱える企業にとっては、出退勤状況の一括確認や、欠員補充の迅速な手配が可能になり、全体の業務効率が向上します。また、警備員一人ひとりの教育・研修の履歴管理や、資格更新のスケジューリングにも活用されており、人材育成にも好影響をもたらしています。
さらに、クラウド上での勤怠データと給与管理システムの連携により、事務処理の自動化が進んでおり、管理部門の業務負担軽減にもつながっています。リアルタイムのデータ共有は、現場と本部の「見える化」を推進し、全体の連携強化にも貢献しているのです。
現場の声を反映するデータ運用
体調管理ツールやヒヤリハット報告の電子化など、現場レベルでもデータを蓄積・分析する動きが進んでいます。スマートフォンやタブレットを活用した報告は、記録の正確性を高めるだけでなく、従業員の健康管理や勤務負荷の把握にも役立ちます。
たとえば、体調不良の申告が一定数集まった現場では、気温や湿度などの環境要因を踏まえたシフト見直しや、水分補給タイミングの再検討が行われることもあります。また、ヒヤリハット事例の共有により、同様のリスクへの注意喚起が可能となり、事故やトラブルの抑止につながります。
蓄積されたデータは、安全対策の改善や業務マニュアルの見直しにも直結します。単なる記録ではなく、「現場の声」として経営層や教育担当者にフィードバックされることで、より実効性の高い対策が講じられるようになるのです。
AIや画像解析との連携強化
AIによる動線分析や混雑予測は、警備の最適化に不可欠なツールとなりつつあります。顔認証やナンバープレート認識などの技術は、イベント会場や大規模商業施設での導入が進んでおり、異常検知の迅速化にも貢献しています。
また、警備員が手にするスマートデバイスとAIシステムを連携させることで、より正確な巡回報告や異常箇所の即時共有が可能となり、現場の判断力も向上します。こうした技術の活用には、導入コストや現場教育の課題もありますが、それを上回る安全性と効率性の向上が期待されており、今後さらに導入が進むと見込まれます。
警備職のキャリアパスと資格制度の進化
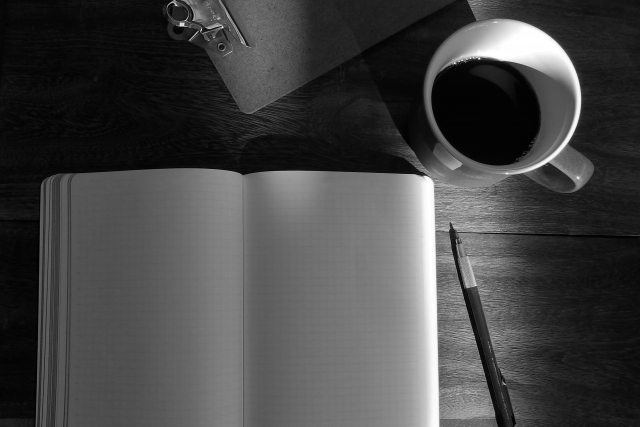
「誰でもできる」から「プロの仕事」へ
警備職は、ただ現場に立つだけでなく、状況判断力や接遇マナー、防災知識、リスクマネジメントなど、幅広いスキルが求められる仕事です。たとえば、施設警備では来訪者への丁寧な対応力が重視され、交通誘導では瞬時の判断力と安全配慮、雑踏警備では群衆心理への理解も重要です。これらのスキルは属人的なものではなく、明確な基準と評価体系に基づくことで、より一層のプロフェッショナリズムが求められるようになっています。
実際、現場で求められる能力を言語化・可視化し、職能に応じた評価制度やキャリアフレームの導入を進めている企業も増えています。これにより、警備職が単なる「仕事」ではなく、成長や達成感を感じられる「専門職」としての地位を確立しつつあります。
資格取得支援と企業の取り組み
国家資格である「警備業務検定(1級・2級)」の取得をはじめ、民間団体による接遇、災害対応、セキュリティ管理の専門講座も拡充され、スキルアップの機会が格段に増えています。こうした学びの場は、日々の業務に必要な知識や技術を体系的に習得できるだけでなく、現場の自信ややりがいにもつながっています。
中には、資格取得にかかる費用を会社が全額補助する制度や、取得後の昇給・昇格を制度的に保証する企業もあり、能力と待遇を連動させる取り組みが進んでいます。これにより、現場で働く警備員にとっても「学ぶ意味」が明確になり、モチベーション向上と定着率改善の効果が出ています。
さらに最近では、eラーニングやスマートデバイスを使った自宅学習支援も増加傾向にあり、多忙な現場でも継続的に学べる環境が整いつつあります。こうした制度は、将来的な人材の質を左右する重要な投資といえるでしょう。
将来の制度整備と新しい職種像
今後、警備士制度や等級制度の導入が進めば、職種としての明確なキャリアビジョンが描きやすくなります。また、防災支援員やセキュリティコンサルタントといった新たな職域が広がることで、若年層や専門人材の参入が促進される可能性もあります。
すでに一部企業では、マネジメント志向の人材を対象にした管理職教育や、異業種経験を活かせるキャリア支援プログラムも始まっています。制度整備と同時に、教育研修の内容も高度化していくことで、警備職は“成長を実感できる仕事”として再評価されていくでしょう。
おわりに
2024~2025年の警備業法改正は、単なる制度の変更ではなく、これからの警備の在り方そのものを問うメッセージとも言えます。
「安心を届ける」仕事としての警備業が、より専門的に、そして柔軟に進化していくチャンスです。制度に振り回されるのではなく、制度を活かして前向きに働く現場づくりが、企業にも、警備員にも求められています。
警備NEXTでは、現場業務の効率化と省人化を実現するための「警備DXにおすすめなシステム5選」の記事もご用意しています。ぜひ参考にしてみてください。
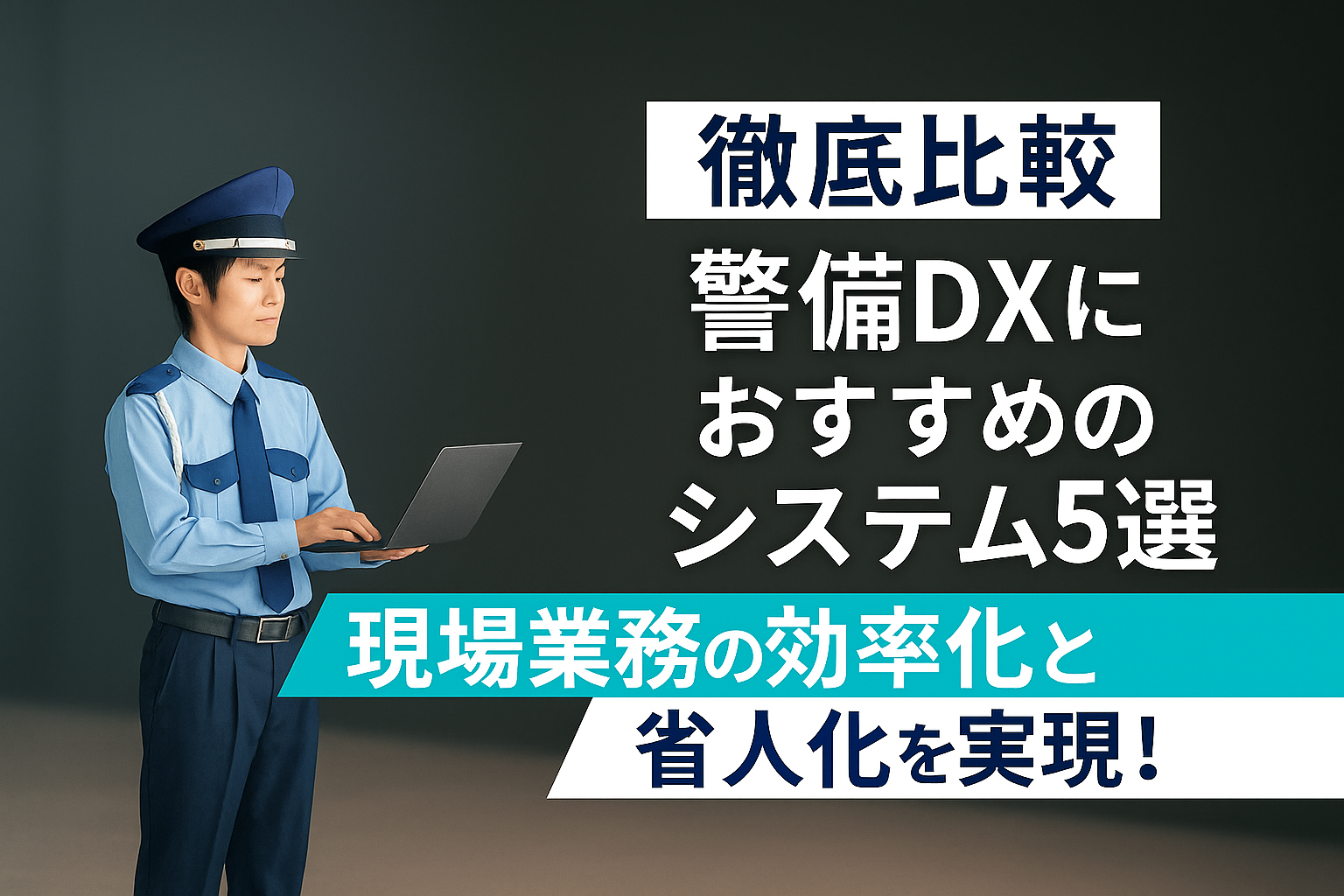
今後も業界を取り巻く社会環境は大きく変化していくでしょう。そんな中でも、警備の価値を高めるために、学び、備え、動き出すことが何より重要です。
