人材の確保や定着が大きな課題となっている警備業界。その中で、現場で働く警備員の皆さんのモチベーションをどのように高め、成長を促していくかは、企業の持続的な発展に欠かせないテーマです。今回は、隊員の皆さんのやる気を引き出すための「フィードバック」の工夫に焦点を当ててご紹介します。
フィードバックは「評価」だけじゃない!警備業務における本質的な意味
フィードバックは評価だけではない
「フィードバック」と聞くと、上司が部下を評価する場をイメージするかもしれません。もちろん、昇給や昇格といった人事評価は、隊員の生活を支え、将来への期待を持たせる上で非常に重要です。しかし、警備業務におけるフィードバックは、それだけにとどまりません。
教育制度だけでは補えない“現場対応力”
警備業法に基づき、警備員は新任教育(新たに警備業務に従事する際に受ける教育)や現任教育(年度ごとに受ける教育)を、定められた時間以上受講することが義務付けられています。この教育を通じて、警備員としての心構えや基礎的な法令、技能を学びます。しかし、実際の現場では日々、予測不能な事態に直面します。たとえば、交通誘導警備で突然の交通事故が発生したり、施設警備で不審火を発見したりと、マニュアル通りにはいかない状況が多々あります。
フィードバックとは「対話」である
フィードバックとは、こうした日々の業務の中で、隊員一人ひとりの行動や成果に対して具体的な情報や意見を伝えることです。
- 商業施設の施設警備で、迷子になった親子への声かけが適切だったか
- 交通誘導警備で歩行者の安全を確保するための誘導方法が的確だったか
といった場面を振り返り、隊員自身の気づきや学びを促すことが大切です。これは単なる「評価」ではなく、隊員の安全意識を高め、業務の質を向上させるための重要な「対話」なのです。
フィードバックが隊員の成長を支える
警備員の仕事は、お客様や社会の安全を守る「サービス業」であると同時に、自己の安全を確保する「プロフェッショナル」としての側面も持ち合わせています。

なぜ警備業務でフィードバックが重要なのか?多角的な視点から考える
警備業務の質を向上させ、隊員の定着率を高める上で、フィードバックは欠かせません。警備業務には、大きく分けて以下のような区分があります。
| 1号警備業務 | 施設警備など、事務所や住宅、興行場などでの盗難等の事故発生を警戒・防止する業務。商業施設、オフィスビル、工場、学校などが対象となります。 |
| 2号警備業務 | 交通誘導や雑踏警備など、人や車両の通行に危険がある場所での負傷等の事故発生を警戒・防止する業務。建設現場やイベント会場、お祭りなどが主な活動の場です。 |
| 3号警備業務 | 運搬中の現金や貴重品、美術品などの盗難を警戒・防止する業務。専門的な知識やチームワークが求められます。 |
| 4号警備業務 | 身辺警護など、人の身体に対する危害発生を警戒・防止する業務。いわゆるボディガードの仕事です。 |
どの警備業務においても、隊員一人ひとりの判断や行動が、お客様の安全・安心に直結します。適切なフィードバックは、隊員のスキルアップはもちろん、事故やトラブルの未然防止にも繋がります。
1. 成長を促す機会になる
フィードバックは、隊員が自身の強みや弱みを客観的に知る良い機会です。 例えば、「あの時の声かけはとても冷静で、お客様に安心感を与えられましたね」といった肯定的なフィードバックは、隊員の自信となり、さらなる成長意欲に繋がります。逆に、改善が必要な点についても、「もう少し早く危険を察知するために、視線の配り方を意識してみましょう」のように具体的なアドバイスをすることで、次に活かせる学びになります。
警備の仕事は、OJT(オンザ ジョブ トレーニング)が中心となることが多く、現場での経験から学ぶことが大部分を占めます。しかし、ただ経験を積むだけでは、同じ失敗を繰り返す可能性があります。管理者が客観的な視点から適切なフィードバックを行うことで、隊員はより早く、より効率的にスキルアップできるのです。
2. モチベーションを向上させる
自身の仕事ぶりを誰かに見ていてほしい、認められたいという気持ちは、誰もが持っているものです。日々の業務の中での小さな成功体験や頑張りを管理者がしっかりと見て、言葉にして伝えることで、「自分の仕事は意味があるんだ」というやりがいやモチベーションが生まれます。
特に、警備業界ではベテランの隊員が多く、新任の警備員が「自分はまだ未熟だ」と感じる場面も少なくありません。そんな時に「〇〇さんのようなベテラン隊員も最初は同じように悩んでいましたよ。でも、今のあなたの〇〇なところは、とても素晴らしいですよ」といった、過去の経験を交えた励ましのフィードバックは、新任隊員の不安を和らげ、安心感を与えます。これが、隊員の定着率向上にも繋がるのです。
3. 組織全体のスキルアップに貢献する
一人の隊員が学んだ成功事例や反省点を、チーム全体で共有することで、組織全体のスキルアップに繋がります。定期的なミーティングなどでフィードバックの場を設けることで、ナレッジ(知識やノウハウ)を蓄積し、より質の高い警備サービスを提供できるようになります。
例えば、ある隊員が不審者への声かけで有効だった具体的な言葉遣いや表情を共有すれば、他の隊員もそのノウハウを学ぶことができます。また、ヒヤリハット事例(事故には至らなかったものの、ヒヤリとしたりハッとしたりした事例)を共有することで、危険予知能力を高め、組織全体のリスクマネジメント能力を向上させることができます。

【事例紹介】やる気を引き出すフィードバックのポイントと実践例
では、具体的にどのようなフィードバックが効果的なのでしょうか。ここでは、現場で実践できる具体的なポイントをいくつかご紹介します。
ポイント1:具体的な行動に焦点を当てる
「今日の警備はよかったよ」といった漠然とした褒め方では、隊員は何が良かったのかが分かりません。大切なのは、「いつ、どこで、何を、どうしたから良かったのか」を具体的に伝えることです。これにより、隊員は自分の何が評価されたのかを明確に理解できます。
(例)施設警備の場合
NG例: 「今日の巡回、良かったよ」
OK例: 「今日の館内巡回、特に3階のバックヤードの鍵のかけ忘れがないか、一つ一つ確認していた姿が素晴らしいですね。お客様の見えない場所でも、きちんと確認する意識が、施設全体の安全に繋がっています。」
このように、具体的な行動を褒めることで、隊員は自分の何が評価されたのかを理解し、次の業務にも活かしやすくなります。また、「なぜそれが良かったのか」という理由まで添えることで、隊員の納得感も高まります。
ポイント2:「なぜ」を一緒に考える
改善を促すフィードバックの際には、一方的に指摘するのではなく、「なぜその行動をしたのか」を隊員に尋ね、一緒に考える姿勢が大切です。これにより、隊員の考え方を理解し、より適切な解決策を共に導き出すことができます。
(例)交通誘導警備の場合
NG例: 「その誘導方法だと危ないから、次はこうしてください」
OK例: 「先ほどの車両の誘導についてですが、どうしてそのタイミングで誘導を始めようと考えましたか? もし、歩行者の安全を最優先に考えるなら、もう少し歩行者の流れが途切れるのを待ってみるのも良いかもしれませんね。」
この対話を通じて、隊員は自律的に考える力が養われ、指示待ちではなく、自ら判断し行動できるプロフェッショナルへと成長していきます。また、管理者は隊員の思考プロセスを理解することで、より的確な指導ができるようになります。
ポイント3:タイミングを逃さない
フィードバックは、できるだけ業務直後に行うのが理想的です。時間が経つと、具体的な状況や感情を忘れてしまい、フィードバックの効果が薄れてしまいます。休憩時間や業務終了後など、少しの時間でもいいので、その日の業務を振り返る時間を取りましょう。
また、フィードバックを行う場所にも配慮が必要です。他の隊員がいる場所では、ポジティブなフィードバックを行うように意識しましょう。オープンな場所での褒め言葉は、周囲の隊員にも良い影響を与えます。逆に、改善点などのネガティブなフィードバックは、後で個別に話す時間を設けるなど、相手のプライドを傷つけない配慮が重要です。個室や人の少ない場所で、冷静に話し合う時間を設けることで、隊員も安心して話を聞くことができます。
ポイント4:キャリアプランを意識したフィードバック
隊員のキャリアパスを意識したフィードバックは、長期的なモチベーション向上に繋がります。警備業界には、警備員指導教育責任者や機械警備業務管理者といった国家資格があり、これらを取得することでキャリアアップが可能です。例えば、将来的に警備員指導教育責任者の資格取得を目指したいと考えている隊員には、日々の業務の中で「新人への指導」や「教育的な視点」を意識するようアドバイスをすると良いでしょう。
「〇〇さんのような冷静な判断力は、将来的に指導教育責任者として新人を教える上で大きな強みになりますよ」といった言葉は、隊員の将来に対する期待感を高め、日々の業務に対する責任感や意欲を引き出します。また、具体的な資格取得に向けたサポート体制(研修制度や資格取得費用の補助など)を提示することで、隊員は企業への帰属意識を高め、長期的なキャリアを築いていきたいと考えるようになります。

フィードバック文化を組織に根付かせるための考察
フィードバックを個々の管理者の裁量に任せるだけでなく、組織全体の文化として根付かせることも重要です。
1. 研修制度の導入
フィードバックの方法や重要性について、管理者向けの研修を実施することも有効です。**「ポジティブなフィードバックの仕方」「効果的な質問の仕方」「傾聴のスキル」**などを体系的に学ぶことで、管理者自身が自信を持ってフィードバックを行えるようになります。
2. 評価制度との連携
フィードバックを、年に数回行われる人事評価の面談だけに限定しないことが大切です。日々のフィードバックと人事評価を連携させることで、隊員は自分の成長がきちんと評価されているという実感を持つことができます。例えば、日々のフィードバックの内容を記録しておき、評価面談の際にその記録を参考にしながら話すことで、より客観的で納得感のある評価が可能になります。
3. 双方向のコミュニケーションを促す
フィードバックは、管理者から隊員への一方的な伝達ではなく、隊員からも管理者へ意見を伝える機会を設けることが重要です。隊員が現場で感じている課題や改善点を自由に発言できる場を設けることで、現場のリアルな声が吸い上げられ、組織全体の改善に繋がります。また、隊員自身が「自分の意見が聞いてもらえている」と感じることで、エンゲージメント(組織への愛着心や貢献意欲)が高まります。
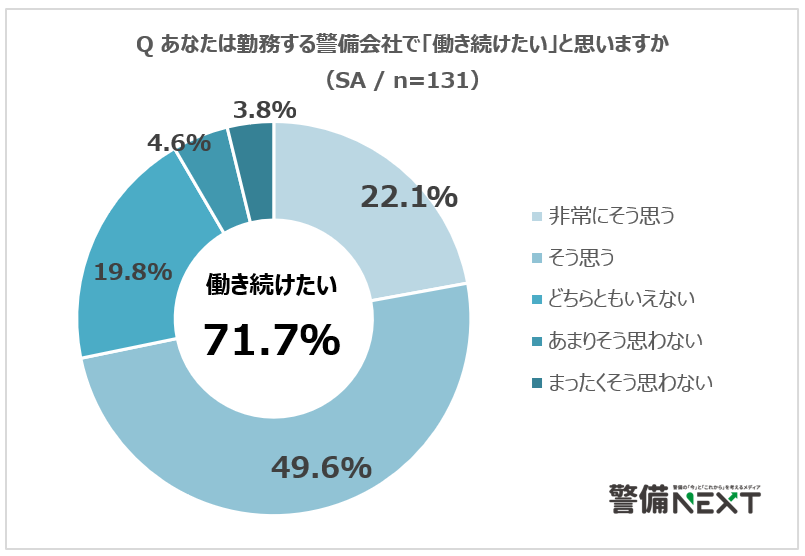
まとめ:フィードバックは「育てる」ためのコミュニケーション
人材育成や定着率向上は、一朝一夕で解決できる問題ではありません。しかし、日々の業務の中で、隊員の皆さんに寄り添い、具体的なフィードバックを継続的に行うことで、一人ひとりの成長を促し、企業全体の力を高めることができます。
警備業は、人の命や財産を守る尊い仕事です。その使命を果たすためには、質の高いサービスを提供できるプロフェッショナルを育てることが不可欠です。ぜひ、今日から「フィードバック」を単なる評価ではなく、「育てる」ための大切なコミュニケーションとして活用してみてください。
この記事が、読者の皆様の現場での人材育成の一助となれば幸いです。また他にも警備NEXTでは警備業界全体の発展にも貢献できる情報をご紹介しておりますので是非ご覧ください。
