「ベテラン警備員が辞めてしまったら、会社はどうなるんだろう…」
そんな不安を抱えたことはありませんか?長年の経験で培われた技術や判断力は、新人には決して真似できない貴重な財産です。しかし、そのノウハウは個人の頭の中や「背中を見て覚えろ」といった属人的な教育方法で終わってしまいがちです。
ベテラン警備員が長年の経験で培ってきたノウハウは、人材育成の大きなヒントになります。彼らが持つ「現場の勘」や「臨機応変な対応力」を組織全体で共有し、新人警備員へと受け継いでいくことができれば、離職率の低下やサービス品質の向上につながるはずです。
この記事では、警備業界の教育担当者、現場管理者、人事担当者の皆さまに向けて、ベテラン警備員のノウハウを組織の力に変えるための具体的な方法をご紹介します。
警備業界が直面する人材育成の課題とノウハウ共有の重要性
警備業は、人の命や財産、安全を守るという、非常に重要な役割を担っています。しかし、その業務は多岐にわたり、交通誘導警備、施設警備、雑踏警備、貴重品運搬警備など、それぞれの現場で求められるスキルや知識は異なります。警備業法に定められた新任教育・現任教育は、警備員としての最低限の知識を身につける上で不可欠ですが、実際の現場ではマニュアルには書かれていない「生きた知識」が求められることがほとんどです。
たとえば、交通誘導警備では、車両の流れや歩行者の動きを瞬時に判断し、危険を未然に防ぐ「予測力」が重要です。これは、長年の経験がなければ培うことが難しいスキルと言えます。施設警備であれば、不審者の特徴を瞬時に見抜く「観察力」や、冷静な状況判断が求められます。雑踏警備では、群衆の心理を読み解き、事故や混乱を未然に防ぐ「洞察力」が不可欠です。
これらのスキルは、座学やマニュアルだけでは習得できません。OJT(オンザ ジョブ トレーニング)を通じて、ベテラン警備員から直接指導を受けることで初めて身につくものです。しかし、「見て覚えろ」という属人的な指導方法では、教える側の負担が大きくなるだけでなく、教わる側も不安を感じ、早期離職につながるリスクを高めます。
厚生労働省の「警備業の人材育成のために」の資料にも、警備業における人材育成の課題として、「教育体制が確立されていない」「OJTが形式的なものになっている」といった点が挙げられています。これらの課題を解決するためには、ベテラン警備員のノウハウを個人のものとして終わらせず、組織全体の共有財産として活用する仕組みを構築することが急務なのです。
ノウハウ共有を仕組み化するための3つの要素
ノウハウ共有を「個人の善意」に頼るのではなく、組織的な仕組みとして定着させるためには、大きく3つの要素が重要になります。
1. ノウハウの「言語化」と「見える化」で共有財産にする
ベテラン警備員のノウハウは、しばしば「なんとなく」「感覚的に」行われていることが少なくありません。この「感覚」を言語化し、誰もが理解できる形に「見える化」することが、ノウハウ共有の第一歩です。
- チェックリストやマニュアルの作成
マニュアルは、法定教育で習得した知識を補完する形で作成することが効果的です。例えば、特定の現場で起こりやすいトラブルとその対処法、使用する警備資機材の注意点、近隣住民への配慮事項など、現場ごとの特性を盛り込んだマニュアルを作成します。この際、ベテラン警備員にヒアリングを行い、「この現場のこの時間帯は、〇〇に注意が必要だ」といった生きた情報を盛り込むことが重要です。 - 写真や動画の活用
警備員の動きや身だしなみ、警棒や無線機などの資機材の正しい使用方法などは、文字だけでは伝わりにくいものです。スマートフォンやデジタルカメラを活用して、写真や短編動画を作成し、マニュアルに組み込みます。視覚的な情報を取り入れることで、新人はもちろん、経験者も自身の動きを客観的に見直し、改善点を発見しやすくなります。 - ナレッジ共有プラットフォームの導入
紙のマニュアルでは、情報の更新や共有に手間がかかります。社内ポータルサイトや専用のアプリ、チャットツールなどを活用し、ノウハウをデジタル化することで、リアルタイムでの情報共有が可能になります。例えば、現場で起きたヒヤリハット事例や成功事例を、写真付きで投稿できる仕組みを設けることで、社員全員が学びの機会を得られます。
2.OJTを「放置」ではなく「育成」の場に変える
現場でのOJT(オンザ ジョブ トレーニング)は、警備員の教育に欠かせないものです。しかし、ただ単に「隣で見て覚えろ」というスタンスでは、新人は不安を感じてしまい、早期離職につながる可能性があります。OJTを効果的な育成の場にするためには、以下の取り組みが有効です。
- OJT担当者の役割と責任を明確化
OJTを行うベテラン警備員に、単なる「指導員」ではなく、「育成担当者」としての役割を与え、その責任を明確にします。具体的には、新人の教育計画を立て、進捗状況を定期的に確認・報告する義務を課すことで、OJTが形骸化するのを防ぎます。 - コミュニケーションシートの活用
厚生労働省の「警備業の人材育成のために」の資料にもあるように、OJTを行う際のコミュニケーションシートなどを活用し、教育担当者が「いつ、何を、どのように教えたか」を記録する仕組みを取り入れるのも一つの方法です。これにより、教育の進捗状況が可視化され、新人警備員も「自分が今、何を学んでいるのか」を理解できるようになります。また、教育担当者自身のスキルアップにもつながります。 - フィードバックの機会を設ける
定期的なフィードバックの機会を設けることで、新人は自身の成長を実感でき、モチベーションを維持できます。また、OJT担当者も新人の成長を間近で見ることができ、自身の指導方法を改善するきっかけにもなります。
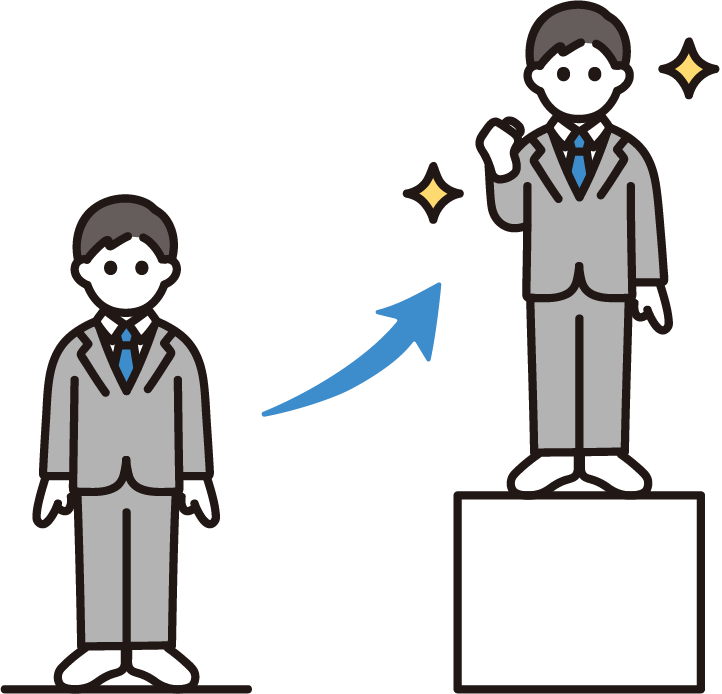
3. 「学びの機会」と「評価制度」でベテランのモチベーションを維持
ノウハウを提供するベテラン警備員のモチベーションを維持することも重要です。長年現場で活躍してきたベテラン警備員にも、新たな学びの機会を提供することで、彼らのキャリアアップ意欲を高めることができます。
- 専門分野の研修・資格取得支援
例えば、施設警備であれば、最新の防犯カメラシステムやAIを活用した警備手法に関する研修、雑踏警備であれば、大規模イベントにおけるリスクマネジメント研修など、専門性を深める機会を設けることで、ベテラン警備員は自身の経験をさらに高めることができます。また、交通誘導警備業務2級・1級などの資格取得を支援することで、専門家としてのキャリアパスを提示できます。 - 指導者としての評価制度の確立
新人警備員の育成に貢献したベテラン警備員を正当に評価する制度も有効です。給与や手当に反映させるだけでなく、「新人教育トレーナー」などの役職を与え、その貢献度を称えることで、ベテラン警備員は自身の経験が会社に必要とされていることを実感し、より積極的にノウハウ共有に取り組むようになるでしょう。 - キャリアパスの提示
ベテラン警備員が「この会社で働き続けると、将来どうなれるのだろうか」という疑問を抱かないよう、キャリアパスを明確に提示することも重要です。現場のリーダーから、教育担当者、さらに管理職へとステップアップできる道筋を示すことで、長期的なキャリアプランを描けるようになり、離職防止につながります。
ノウハウ共有は、人材育成を超えた「会社の未来」をつくる投資
ベテラン警備員のノウハウ共有は、単なる新人教育やOJTの改善にとどまりません。これは、会社の未来を築くための重要な「投資」と捉えるべきです。
社員の定着率向上: ノウハウを学ぶ機会が豊富にある職場は、新人警備員にとって「成長できる場所」になります。また、メンター制度などを通じて、孤独を感じることなく安心して働ける環境は、早期離職を防ぐ大きな力となります。
サービス品質の安定と向上: ベテラン警備員のノウハウが組織全体で共有されれば、個人のスキルに依存することなく、警備業務の品質を安定させることができます。また、新人が早期に一人前の警備員として活躍できるようになることで、会社全体のサービス品質向上につながります。
ベテラン警備員のモチベーション維持: 自分の経験や知識が会社に役立っているという実感は、ベテラン警備員にとって大きなやりがいになります。さらに、後進を育成する過程で、自身の業務を客観的に見つめ直す機会にもなり、新たな学びへとつながる好循環が生まれます。
警備業界は、今、まさに変化の時を迎えています。警備業法に定められた法定教育(新任教育20時間以上、現任教育10時間以上)は、警備業務の基盤を築く上で不可欠ですが、それだけでは時代の変化に対応することは難しいでしょう。ベテラン警備員の持つ「生きた知識」を共有し、組織全体の知恵として活用していくことで、警備会社は「単なる労働力の提供」から「高度なサービスを提供する専門家集団」へと進化できるのではないでしょうか。
まとめ:ノウハウ共有で人材育成の好循環を生み出しましょう
この記事では、ベテラン警備員のノウハウ共有を仕組みにするための方法についてお話ししました。最後に、要点をまとめておきましょう。
- ノウハウの「言語化」と「見える化」: ベテランの経験を動画マニュアルやチェックリストに落とし込み、誰でも学べる形にしましょう。
- OJTを「育成」の場に: OJT担当者の役割を明確にし、計画的に新人警備員を育成する体制を整えましょう。
- ベテラン警備員のモチベーション維持: 新しい学びの機会や、指導者としての評価制度を設け、ベテラン警備員の活躍を後押ししましょう。
人材育成は一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、今ある貴重な財産(ベテラン警備員のノウハウ)を最大限に活用し、人材育成を組織的な仕組みにすることで、必ずやその努力は実を結びます。
「まずは小さな一歩から」で構いません。今日からできることとして、ベテラン警備員の方に「新人時代に困ったことは何でしたか?」と、簡単なヒアリングから始めてみてはいかがでしょうか。その一言が、貴社の未来を切り開く大きな一歩になるかもしれません。
