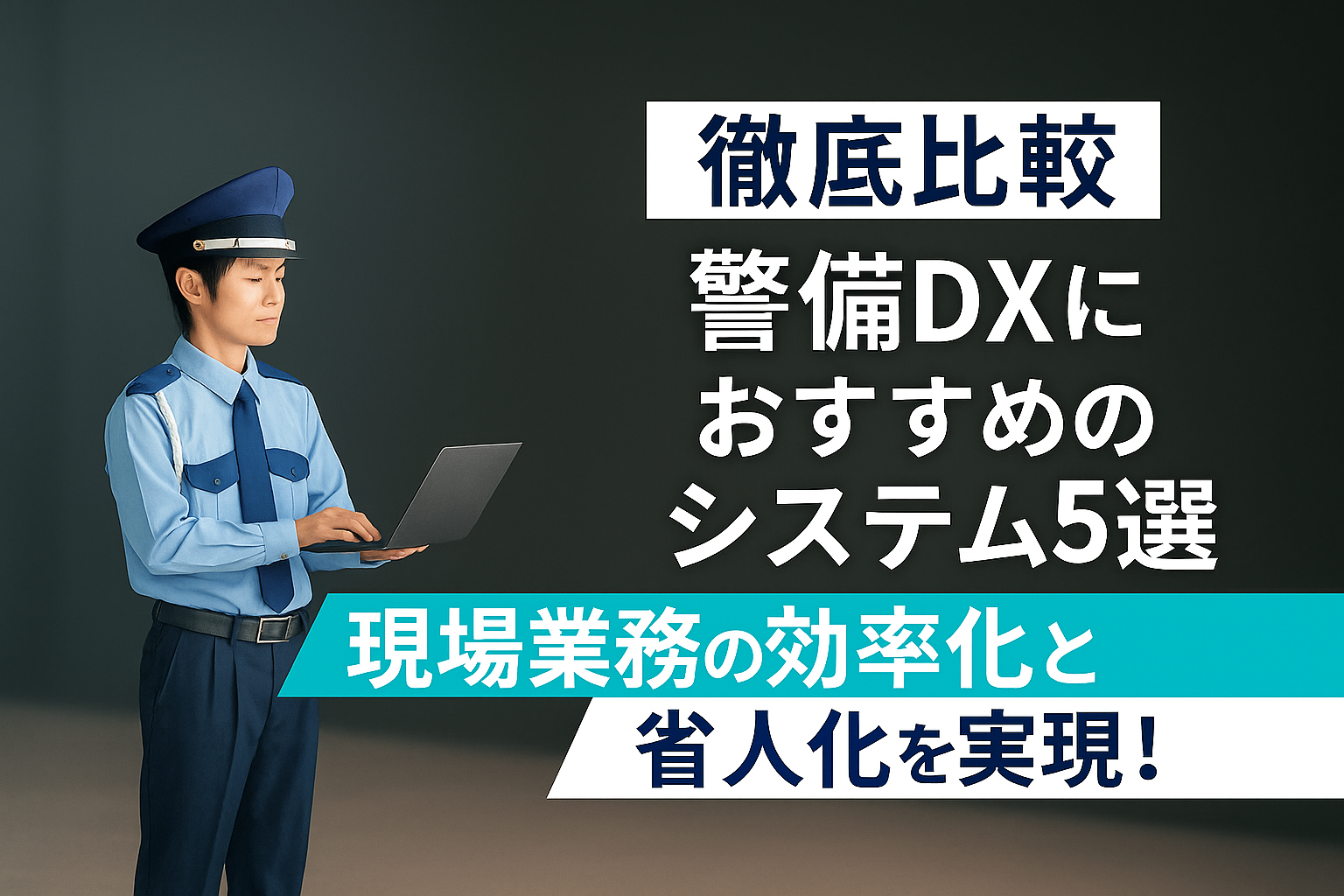警備業界は今、大きな変化の渦中にあります。人材確保の難しさや業務の多様化といった課題が浮き彫りになるなか、ITやAIを活用した“警備DX”が急速に進んでいます。特に、施設警備や巡回警備、雑踏警備(多くの人が集まる場の秩序維持)などの現場では、効率化と安全性を両立させるための新しい手段として、テクノロジーの活用が欠かせません。その中で注目されているのが「ウェアラブルカメラ」です。
小型で装着可能なこの機器は、警備員の視点で映像を記録・配信することで、業務の可視化と安全性の向上を実現します。本稿では、ウェアラブルカメラの基本的な役割、活用のメリットと注意点、導入事例、そして今後の展望について詳しく解説していきます。
ウェアラブルカメラとは? 警備業務における基本的な役割
ここでは、ウェアラブルカメラがどのような機器であり、警備現場においてどのように活用されるかを解説します。導入の基本を理解することで、活用の可能性がより明確になります。
ウェアラブルカメラの定義と機能
ウェアラブルカメラとは、体に装着して周囲の映像や音声を記録・送信できる小型カメラのことです。肩や胸元、帽子、眼鏡に装着できるタイプが一般的で、警備業務中に両手を使えるという点で実用性が高く、巡回警備や交通誘導などでも活躍しています。
主な機能には以下のようなものがあります:
- 高画質の録画・ライブ配信(ストリーミング)
- GPS機能との連動による位置情報の取得
- 暗所対応・赤外線機能付きの夜間対応
- 音声記録機能
- 長時間稼働バッテリーや遠隔操作機能
これらの機能によって、警備員が現場で遭遇した事象をリアルタイムで記録・共有し、迅速な対応が可能になります。
警備業務での活用シーン
警備現場ではさまざまな用途でウェアラブルカメラが活用されています。たとえば:
- 巡回時の記録:不審者や異常発見時の映像をそのまま証拠として保存。
- リアルタイム監視:指令室や上司が映像を確認し、現場へ即時指示。
- スタッフ教育:新人警備員の研修教材としてベテランの対応記録を使用。
- 事故検証:トラブル発生時の状況を正確に把握するための記録ツール。
こうした用途を通じて、業務の透明性と信頼性が高まり、「見える警備」の実現につながっています。
活用の実際:導入事例と現場の声
実際の現場でウェアラブルカメラがどのように使われているのか。導入事例をもとに、その効果と課題を具体的にご紹介します。
事例1:大型商業施設での巡回業務
関東地方にあるショッピングモールでは、警備会社と連携して巡回警備員全員にウェアラブルカメラを導入しました。映像は本部に設置された管制室にリアルタイムで送られ、異常を察知した際には即座に指示が出せる体制を構築しています。
「映像があることで“見える化”が進み、館内の安全対策全体のレベルが上がりました。警備員の対応内容が記録されるので、誤解やクレームの抑止にも役立っています」
この施設では、録画された映像を月ごとにアーカイブ化し、トラブル発生時には再確認する体制も整備されています。
事例2:地域イベントにおける雑踏警備
関西地方の地方自治体が主催する夏祭りでは、警備スタッフにウェアラブルカメラを配布し、雑踏警備に活用しました。来場者が密集する時間帯では、混雑状況を本部が映像で把握し、臨機応変な誘導や安全確保に役立てられました。
「一人では対応できない場面でも、映像を通じて本部が状況を理解してくれる安心感があります。とくに暗くなってからの警備では、ナイトモードが心強かったです」
この事例では、自治体・主催者・警備会社の三者連携の要となったのが、映像情報の共有でした。これにより、警備力の全体最適が実現されました。
導入時の注意点:コスト・プライバシー・運用設計

便利なツールである一方、ウェアラブルカメラの導入には注意すべき点も多くあります。ここでは、費用面や法的観点、実務面での課題を整理します。
コスト面の課題
ウェアラブルカメラの本体価格は、1台あたり約2万〜10万円。機能性やメーカーによって大きく異なります。さらにクラウド録画サービスやAI解析機能を活用する場合、月額費用が1台あたり3,000〜8,000円程度かかることもあります。導入の際は、全体コストと得られる効果のバランスを慎重に検討する必要があります。
プライバシー保護の観点
映像には、来場者やテナントスタッフなどの個人情報が映り込む可能性があるため、法的リスクを見据えた運用が求められます。
- 撮影中であることを明示する掲示やアナウンスの設置
- 録画データの保存期間・アクセス制限の明確化
- 外部提供時の手続き整備(契約書・同意書など)
スタッフへの教育と運用整備
機器を導入しても、適切に使えなければ効果は半減します。とくに以下の点での教育が重要です。
- 撮影開始・終了のルールと操作方法
- 不具合時の対応方法(例:バッテリー切れ・録画停止)
- データの取り扱いに関する意識づけ
職場での「監視されている」という感覚を払拭するためには、導入の目的や利点を丁寧に共有し、スタッフの不安を事前に取り除く姿勢も欠かせません。
今後の展望:ウェアラブルカメラは警備DXの起点となるか
ウェアラブルカメラは単なる記録ツールにとどまらず、警備業務全体のデジタル化を推進する起点になり得ます。ここでは、その将来性と発展可能性を考察します。今後は、ウェアラブルカメラとAI解析との連携によって、映像から「異常行動の自動検知」「音声認識によるSOS検出」などの高度な警備が可能になると予想されます。さらに、他のシステム(入退室管理、ロボット監視、勤怠管理など)との統合により、警備オペレーションの最適化も現実味を帯びてきています。
一方で、急激なデジタル化により、現場スタッフとの温度差が生じるケースもあるため、「段階的な導入」「小規模試行」「現場の声の吸い上げ」といった丁寧なアプローチが重要となります。
まとめ:記録から共視へ、警備の新しいスタンダード
ウェアラブルカメラは、警備員の視点を共有することで、“現場の可視化”を可能にするツールです。業務の透明性を高め、対応の迅速化や教育への活用、安全性の強化といった多くのメリットがあります。一方で、コスト面・プライバシー・スタッフ教育といった課題もあるため、計画的かつ柔軟な導入が求められます。
今後、警備DXの進展に伴い、ウェアラブルカメラは「記録するカメラ」から「共に見るカメラ」へと進化していくことでしょう。まずは小規模な導入から、貴社の警備品質を一歩前に進めてみてはいかがでしょうか。
警備NEXTでは、現場業務の効率・省人を実現するためのDX化について「警備DXにおすすめなシステム5選」の記事もご用意しています。ぜひ参考にしてみてください。