警備業界では人手不足が深刻化しており、特に20代の若手警備員の定着が大きな課題となっています。
厚生労働省の統計によると、警備業の有効求人倍率は他業種に比べても高く、全職業の平均が1.21倍であるのに対し、警備業はおよそ7倍と慢性的な人材不足が続いています。その一方で、20代の警備員は「体力的にきつい」「将来のキャリアが見えにくい」といった理由から、入社から数年以内に離職するケースが少なくありません。
こうした現状を踏まえ、本記事では若手警備員の定着率を高めるための育成術を3つのポイントに絞って紹介します。現場での具体的な工夫や教育担当者が実践できる施策を取り上げますので、自社の取り組みに活かしていただければ幸いです。
ポイント1:安心感を与える「新人教育」とフォロー体制
初期教育の重要性
警備員として働き始める20代にとって、最初の数週間は大きな不安を伴います。交通誘導や施設警備、雑踏警備など、仕事内容は多岐にわたり、警備業法や現場ルールの理解も必要です。
厳密には、警備業法に基づき新任教育(20時間以上の法定研修)が義務付けられています。こうした教育の質が、現場での不安軽減や定着率に大きく影響します。
フォローアップの仕組みづくり
効果的なのは「メンター制度」や「同行指導」です。経験豊富な先輩が数週間から数か月にわたりサポートすることで、若手は安心して現場業務を学べます。
さらに、研修後に定期的なフォロー面談を行うことで、本人の悩みや不安を把握でき、早めのケアにつながります。
ポイント2:キャリアアップ研修で未来を描かせる
キャリアパスが見えないと定着しない
20代の警備員の離職理由として多いのが「この仕事を続けても将来が見えない」という声です。特に若手は、長期的な成長や役職昇進のイメージを持てないまま働き続けることに不安を感じます。
研修と資格取得支援がカギ
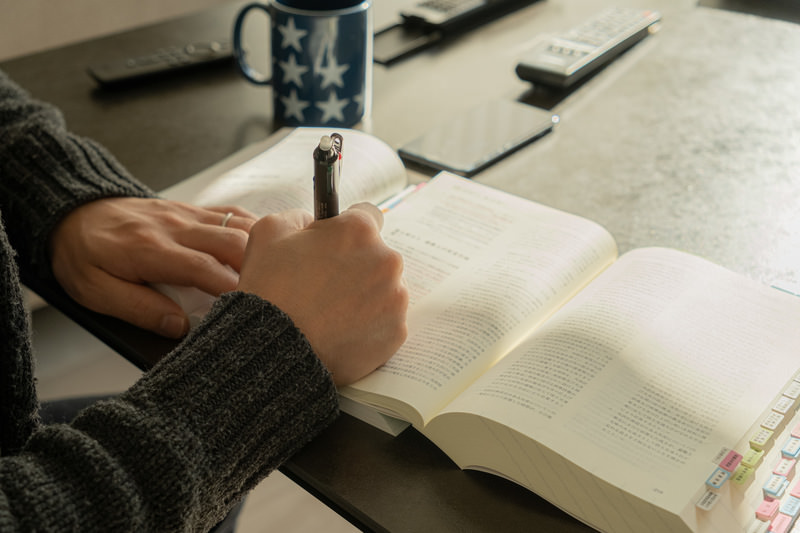
全国警備業協会が実施する「警備業務検定」や、都道府県公安委員会が管轄する「警備員指導教育責任者」など、国家資格の取得は若手の大きなモチベーションになります。
企業側が受験費用の補助や学習環境の提供を行えば、「この会社なら成長できる」と実感でき、定着率の向上に直結します。
事例紹介
ある中堅警備会社では、入社3年目までに「交通誘導2級」または「施設警備2級」の取得を目標とし、合格者には昇給を約束する制度を導入しています。社内報告によれば、この仕組みにより若手社員の定着率が改善したとされています。
ポイント3:働きやすさを支える労働環境づくり
ワークライフバランスの確保
若手警備員は、体力的な負担だけでなく、シフトの不規則さから生活リズムが崩れることに不満を抱えやすい傾向にあります。
シフト希望をできる限り反映させる仕組みや、休暇取得を奨励する制度があることで「長く続けられる職場」と感じてもらいやすくなります。
給与・待遇面の透明化
「ディップ株式会社」が実施した警備員へのアンケート調査では、「仕事内容の割に給与が低いから」を離職理由とする回答が約26%あり、給与水準の低さが離職の要因の一つであることが明らかになっています。
給与そのものをすぐに引き上げるのが難しい場合でも、前払い制度の導入や交通費の全額支給、資格手当の充実など、若手が実感しやすい形で待遇改善を図ることが効果的です。
健康管理と安全配慮
特に夏場の交通誘導警備では、熱中症リスクが高まります。
2024年4月の改正労働安全衛生法施行規則により、WBGT値(暑さ指数)28以上での休憩が義務化されました。現場での水分補給・休憩時間の確保を徹底することも離職防止に直結します。
若手警備員が「ここで働きたい」と思える職場づくりへ
若手警備員の定着を高めるには、単なる給与や待遇の改善だけでなく、「安心できる教育」「未来を描けるキャリア支援」「働きやすい環境」の3つが欠かせません。
教育担当者や現場管理者が、日々の業務のなかでこれらの要素を意識的に取り入れ、若手一人ひとりに寄り添うことが、定着率向上への第一歩となります。
人材不足が続くなかでも、「若手に長く働いてもらえる環境を一緒に築いていく」という視点が、これからの警備業界には大切です。
警備NEXTでは、現場で役立つ知識や警備員の声をこれからも発信していきます。日々の勤務に少しでも役立ててもらえたら幸いです。
